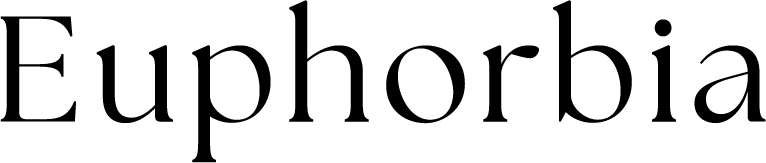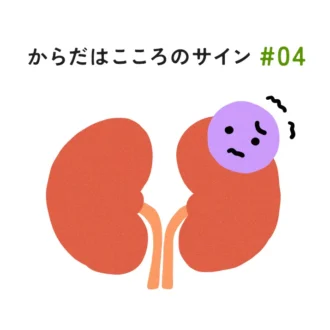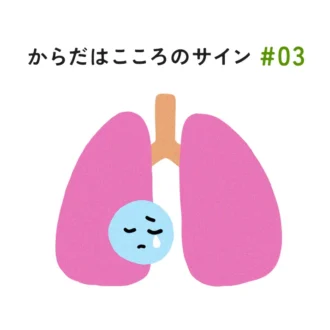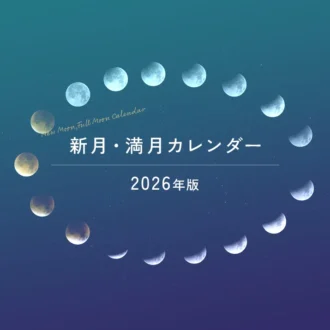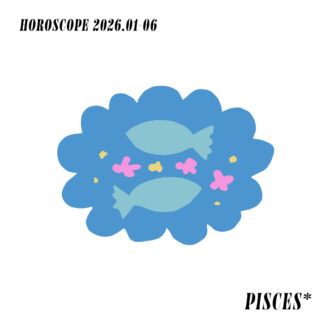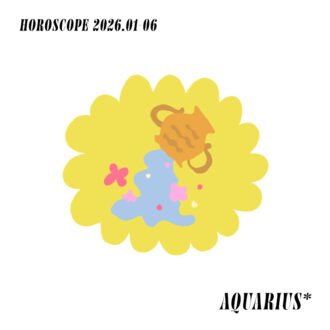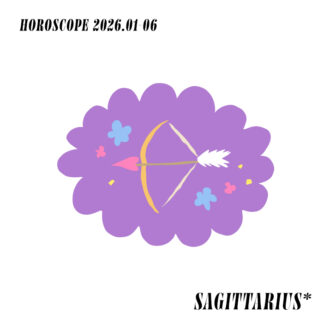「なぜかイライラが止まらない…!」肝臓と怒りの関係【からだはこころのサイン #01】
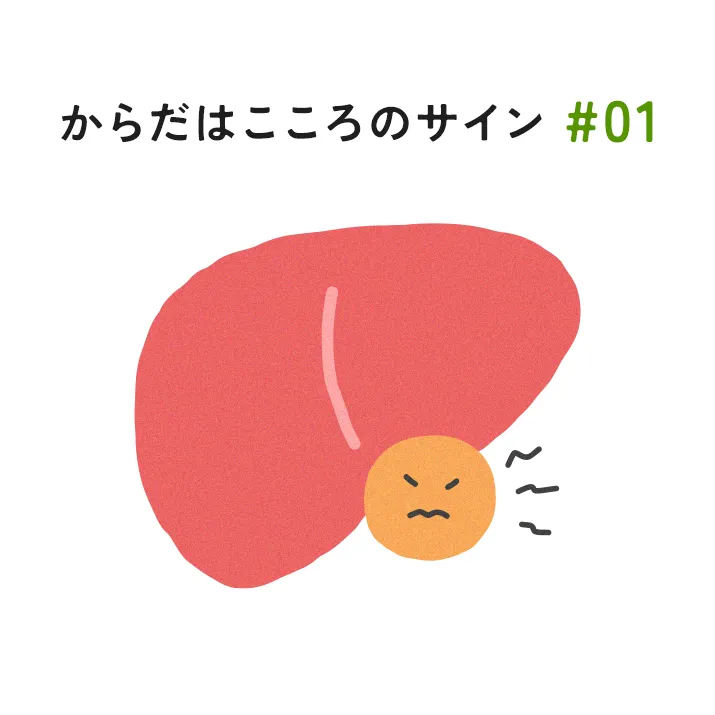
Release 2025.09.03 / Update 2025.12.02
毎日の暮らしの中で、ふとした瞬間にイライラが込み上げてくることはありませんか?
朝の支度のときに子どもが思うように動いてくれない。
仕事中に、同僚のちょっとしたひと言にカチンときてしまう。
パートナーの何気ない態度に「どうして私ばかり…」と心の中でつぶやく。
そんなふうに、日常の小さな出来事でイライラが込み上げてきて、あとから「なんであんなに怒ってしまったんだろう」と落ち込む…
もしかしたらその怒りは、からだからのサインなのかもしれません。
そして、そのサインを抱きとめている臓器のひとつが肝臓だといわれています。
「え、怒りと肝臓が関係あるの?」
この記事では、東洋医学の視点から「肝臓と怒り」の関係をひも解きながら、日常に取り入れられるやさしいセルフケアをご紹介します。
INDEX
肝は怒りをためる臓器(東洋医学の視点から)
東洋医学では、肝臓は「疏泄(そせつ)」=気や血(エネルギー)の流れを整える役割を担っていると考えられています。
まるで体の中にある交通整理員のように、心とからだのエネルギーがスムーズに巡るよう調整してくれているんです。
でも、この流れが詰まってしまうとどうなるでしょう?
たとえば道路が渋滞すると、ほんの小さな信号の遅れにもイライラしてしまうように、心の巡りが滞ると、ささいな出来事でも強く反応してしまうのです。
だから、私たちが「なんでこんなことで怒っちゃうんだろう」と感じるとき、その裏側では肝のエネルギーが詰まって、SOSを出していることが多いのです。
実際にこんなサイン、出ていませんか?
- ため息ばかり出てしまう
- 寝つきが悪い、考えごとで頭が休まらない
- 目がしょぼしょぼして疲れやすい、視界がかすむ
- 生理前にイライラや張り感が強くなる
これらは「心の問題」ではなく、体からのメッセージなんです。
つまり「あなたの感情は体に記録されている」ということ。
ここで気づいてほしいのは、怒りや苛立ちは単なる“性格の問題”だけではない、ということ。
肝臓が「もうがんばりすぎないで」「少しゆるめてほしい」と訴えているのです。
だからもし、最近ため息が増えたなと感じたら、それは「もっと自由に深呼吸していいよ」という宇宙からのサイン。
もし夜になかなか眠れないとしたら「今日一日よくやったね、あとは自然に任せていいよ」という合図。
怒りはあなたを壊すためにやってくるのではなく、肝臓を通して「本当の自分の声」を知らせてくれているのです。
怒りは、悪者じゃない
怒ってしまう自分を「大人げない」と責めたり、「優しくできなかった」と落ち込むこと、ありますよね。
でも本当は、怒りはあなたを守るために生まれるもの。
「ここから先は苦しいよ」
「もっと大切にしてほしい」
そう伝える、心からの合図でもあるのです。
繊細で、周りに優しくしてきた人ほど、自分の想いを後回しにしてしまう。
その優しさの裏で溜めこんだ気持ちが、ようやく顔を出しているのです。
だから、怒りは悪ではなく愛のメッセージ。
「私は私を大切にしたい」
「私はここにいていい」
その声を受けとめるところから、癒しは始まります。
怒りの裏に隠れている、もうひとつの本音
ただ、怒りにはもうひとつの顔があります。
それは「自分の正しさを通したい」という気持ち。
誰かに理解されなかったとき、希望が叶わなかったとき、心がむっと反応してしまう。
それは自然なことだけれど、根っこには「自分のものさしだけで相手を見てしまう」瞬間が隠れているのかもしれません。
でも、相手にも相手の大切にしている視点があります。
その存在に気づけると、怒りは少しやわらぎます。
イライラしたときに「私はいま、自分の正しさを守ろうとしているな」と気づいてみる。
そして「相手にも相手の大切にしている視点がある」と思い出してみる。
それだけで心の硬さはほぐれ、共に歩む余白が生まれます。
怒りは「自分の思い」と「相手の思い」をどう調和させるかを教えてくれる、人生からの小さな練習問題なのかもしれません。
イライラを抑えたい…!肝臓を癒すためにできること
怒りをなくそうとする必要はありません。
大切なのは「怒りを感じてもいい」と受けとめながら、肝臓に少しの余白を与えてあげること。
一度に全部をやろうとしなくても大丈夫。
「これならできそう」と思えるものを一つ選んで試してみてください。
その小さな一歩が、確実にあなたの心と体をやわらかく変えていきます。
朝の時間におすすめ
レモン入りのお湯を飲む
朝いちばんに飲むと、夜の間に溜まった老廃物を流してくれて、肝臓が軽くなります。 酸味は東洋医学で「肝」に働きかける味。気の巡りを助けるので「今日は一日がんばれるかも」という前向きなスイッチが入ります。
ブロッコリーやキャベツを食卓に足す
朝食に添えるだけで、解毒酵素の働きを助け、肝臓が抱え込んだ余分なものを出してくれます。 前の晩に食べすぎたり飲みすぎたりした翌朝にもおすすめ。
昼間に意識したいこと
「いい人」をお休みする
たとえば、職場で頼まれごとをされたときに「今日はちょっと無理かも」と言ってみる。
それだけで肝臓は「やっと本当の声を出せた」と安心します。
無理に笑顔を作らない時間を持つことが、心にも体にも呼吸の余裕を取り戻してくれます。
ハーブティーで気分を整える
カモミールティーは、自律神経を落ち着けて肝臓の緊張をゆるめます。
胃にもやさしく、ストレスで食欲が乱れやすいときにもぴったり。
ほうじ茶は香ばしい香りがリラックスを誘い、食後に飲むと消化を助けて肝臓の負担を軽くしてくれます。
カフェインが少ないので夜にも安心。
緑茶は、カテキンの抗酸化作用が肝臓を守り、テアニンの香りが気持ちを穏やかにします。
カフェインが気になる方は、薄めに淹れるのがおすすめです。
相手の視点を尊重する
イライラしたときに、「相手にも相手の大切にしている視点がある」と思い出してみる。
返事をする前に一呼吸おいて、「あなたはこう思ってるんだね」とくり返してみる。
それだけで関係の空気が少しやわらぎ、怒りが和らいでいきます。
夜の時間におすすめ
しじみやあさりのスープをいただく
一日の終わりに、肝臓を支えてくれるタウリンたっぷりのスープを。
「今日はよく働いたね」と労ってあげるような一杯です。
アルコールを飲んだ日や疲れがたまっているときには特に効果的。
肝臓に手をあてて「ありがとう」を伝える
ベッドに横になったとき、右のあばらに手を添えて深呼吸。
「支えてくれてありがとう」と心の中で伝えるだけで、肝臓の緊張がふっとほどけます。
不思議なことに、この習慣を続けると眠りやすくなったり、朝の目覚めが楽になったりする人も多いんです。
サプリメントでやさしくサポートする
食事で補うのが理想ですが、忙しい日々の中ではサプリメントが頼もしい味方になってくれることもあります。
ミルクシスル(マリアアザミ)
ヨーロッパでは古くから「肝臓の守護ハーブ」と呼ばれ、解毒や修復をサポートすると言われています。
肝臓に溜まりやすい疲れをやさしくほどいてくれる存在です。
ビタミンB群
特にB1・B2・B6・B12はエネルギー代謝を助け、肝臓が働きやすい環境を整えてくれます。
疲れやすい人、ストレスを抱えやすい人におすすめ。
タウリン
しじみや牡蠣に多く含まれる成分。
サプリメントで補えば、肝臓の解毒や代謝をしっかり支えてくれます。
ビタミンEやオメガ3脂肪酸
ナッツや青魚から摂れる栄養素。
血流を良くし、炎症をやわらげることで肝臓の負担を軽くします。
サプリはあくまでも補助として取り入れてみてください。
毎日の生活の中で、まずは自分を大切にすること。
この習慣と組み合わせることで、本当の力を発揮します。
おわりに
怒りは、あなたが未熟だから生まれるのではありません。
それは「ほんとうはこうしたかった」という心の奥の声であり、行き場をなくしたその声を、肝臓がずっと黙って抱きしめてくれていたのです。
また、怒りの奥には「自分の正しさ」が潜んでいることもあります。
そのとき「相手にも大切にしている視点がある」と思い出せたら、怒りはやさしくほどけていきます。
今回ご紹介した小さな実践は、すぐに大きな変化を生むものではないかもしれません。
でも、それらを重ねていくうちに、心とからだは少しずつ、でも確かに変わっていくと思います。
そしてその変化はやがて、「私は私を大切にしていい」という確かな実感となって、あなたを支えてくれるはずです。