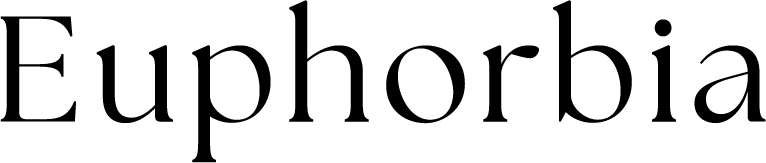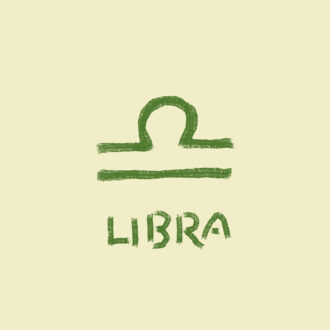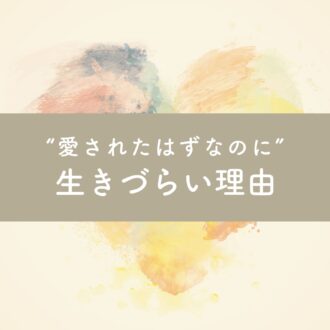親とわたしの境界線がわからない。「愛されたはず」なのに生きづらい理由
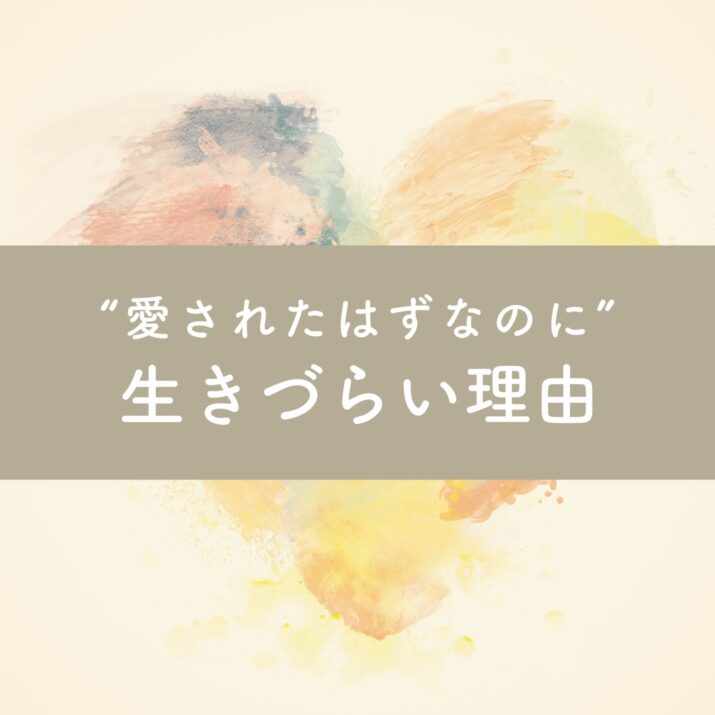
Release 2025.08.07 / Update 2025.08.07
親との関係に、ふと苦しくなるとき。
理由もわからず涙があふれたり、誰かのひとことで心がちくりと痛んだり。
そんな経験、ありませんか?
「もっとわかってほしかった」
「なんで、あのとき抱きしめてくれなかったの?」
「わたしばかり我慢していた気がする……」
そんな想いを抱えてきた人は、決して少なくありません。
でも、こう感じる自分を責めたり、「親を悪く思うなんてよくない」と言い聞かせて、ずっと胸の奥にしまってきた方も多いのではないでしょうか。
わたしたちは今、こんなふうに問い直すことができるかもしれません。
その痛みは、本当に「親のせい」だったの?
それとも、「愛されなかった」という思い込みだったの?
この問いかけは、誰かを責めるためでも、苦しみを無理に手放すためでもありません。
それはむしろ、「誰も悪くなかった」と気づいていくための、魂の目覚めのプロセス。
安心していいのです。ゆっくりで大丈夫です。
わたしたちは、やさしく自分自身の内側に耳を傾けていくことができます。
INDEX
1. 愛着障害って、どういうこと?
わたしたちが「生きづらい」と感じるとき、その根っこには幼少期の愛着のゆらぎがあることがあります。
心理学ではこれを「愛着障害」と呼びます。
とくに、親との関係の中で「安心して甘えられなかった」「自分の気持ちを受け止めてもらえなかった」という体験があると、人は深いところで「自分には価値がない」「愛される資格がない」と信じこんでしまうことがあります。
心理学者ジョン・ボウルビィとメアリー・エインズワースによると、愛着にはいくつかのスタイルがあります。
- 安定型(安心して愛される感覚を持てる)
- 不安型(見捨てられる不安に敏感)
- 回避型(人に近づかれることを恐れる)
- 混乱型(愛と恐れが混在し、反応が一定でない)
こうした愛着スタイルは、恋愛や人間関係、自分自身との向き合い方にまで深く影響を与えます。
しかし、こう考えてみます。
「愛着のゆらぎ」とは、魂が「わたしだけの宇宙」をつくるために、あえて通ることを選んだゆらぎだったのではないかと。
完全な安心ではなく、すこしの不安やすれ違いがあったからこそ、わたしたちは「ほんとうの自分とは?」と問い始めるのです。
もしかしたら、愛着の痛みはただの傷ではなく、「本当の自分に目覚めるためのサイン」なのかもしれません。
2. 「母の機嫌を読むこと」が生きる術だったわたしたちへ
赤ちゃんにとって、母親は世界そのものです。
そのぬくもり、声の調子、目の動き、息づかい、笑顔・・・すべてが「生きるための法則」として、心とからだに深く刻まれていきます。
母の笑顔=安心。
母の不機嫌=危険。
そんなふうに、世界の安全は「母の状態」にすべて結びついているのです。
これは心理学では「融合状態」とも呼ばれます。
とくに発達心理学者マーガレット・マーラーは、子どもが成長とともに母親から心理的に分離し「自分」を確立していくプロセスを「分離個体化理論」として示しました。
この理論では、赤ちゃんが母親と“ひとつの存在”だった状態から、徐々に「母とは別の存在である自分」を見つけていく過程を、いくつかの段階に分けて捉えています。
たとえば、以下のように成長の段階がスムーズに進むと、子どもは「安心して母から離れ、自分の人生を歩く」ことができるようになります。
- はじめは、母と自分の区別がまったくついていない「共生」の時期
- やがて少しずつ母から離れ、外の世界を探索する「分離」の時期
- でも、離れることへの不安で甘えたくなる「回帰」の時期
- そしてようやく、「わたしはわたしでいい」と感じられる「個体化」の確立へと向かう
でももし、「泣いても抱っこしてもらえなかった」、「感情を出すと叱られた」、「いい子でないと受け入れてもらえなかった」などの体験があると、子どもはこう学びます。
「わたしは、わたしのままでいては危ない」
「母の機嫌を読むことが、生き延びる術だ」
このようにして、“自分を消す”ことで愛を得ようとする心のクセが、知らないうちに刷り込まれていくのです。
また、だれかの「痛み」と、あなたの「痛み」が重なる
こんなふうに感じている人も、実はとてもたくさんいると思います。
だからどうか、思い出してみてください。
あなたの心が選んだ“生き方”は、誰かに合わせるためではなく、生きのびるための、静かな勇気のかたちだったことを。
でも、その方法ではもう、生きづらくなってきた。
だからこそ今、「母とわたしは、どこまでが同じで、どこから違うのか」という問いが、やさしく浮かびあがってくるのかもしれません。
3.「毒親」だったかもしれない。でもそれは目覚めのはじまりだった
「親のせいで、わたしはこんなふうになってしまった」
そんなふうに感じることはありませんか?
過干渉だった、感情的に怒鳴られた、無関心だった、愛されている実感がなかった・・・
こうした体験から、「毒親」という言葉で語られることがあります。
その言葉に救われた人もいれば、反対に苦しくなった人もいるかもしれません。
「親を悪者にしたくない」のに、苦しいあなたへ
たとえば、こう思っている人もいるのではないでしょうか。
「本当は、親を責めたくないんです」
「でも、どうしても苦しみが消えないんです」
その気持ち、とてもよくわかります。
だからこそ、こう問いかけてみたいのです。
「もし、その親との関係に、“魂の約束”があったとしたら?」
魂の視点で見えてくる「痛みの意味」
スピリチュアルな視点では、魂は生まれる前に自らの人生をある程度設計してくると考えられています。
どんな家庭に生まれるか、どんな学びを選ぶか。
その中には、「あえて愛されにくい親を選ぶ」ということも、含まれている場合があるかもしれません。
なぜそんな選択をしたのか?
それは、“母という宇宙”から切り離され、自分だけの宇宙を生きるため。
つまり、厳しさや欠け、すれ違いは、わたしたちの魂が「自分の道」を歩きはじめるための、静かなスイッチだったのかもしれません。
親を超えて、自分という宇宙を生きる
そう考えると、親との関係は「敵」ではなく、「わたしがわたしになる」ための出発点だったといえるのかもしれません。
でも、それは「親を許さなければいけない」ということではありません。
怒ってもいいし、悲しんでもいいし、「もっと愛してほしかった」と泣いても、いいのです。
そのすべてを通って、わたしたちは少しずつ、母の宇宙から、自分の宇宙へと旅をしていくのです。
4. 「親なんだから○○してくれるはずだった」という幻想
「親なんだから、私の気持ちをわかってくれるはずだった」
「無償の愛をくれるのが“親”というものだと思っていた」
「親は子どもを絶対に傷つけてはいけない存在だよね?」
こんなふうに思ったこともあるかもしれません。
でもそれはもしかしたら、現実の親ではなく、社会や文化がつくりあげた「理想の親像」だったのかもしれないのです。
本当は、親もただの“ひとりの人間”だった
わたしたちの親もまた、傷を抱えたまま大人になり、完璧とはほど遠いまま「親」という役割を背負った人でした。
怒りをコントロールできなかったり、愛し方を知らなかったり、自分を守ることで精一杯だったり・・・そんなふうに不完全なまま、わたしたちの前に立っていたのです。
でも、だからといって、「自分の傷はたいしたことなかったんだ」と思う必要はありません。
あなたが感じた痛みは、本物です。
たとえ相手が悪気なくしていたことだったとしても、あなたの心には今でも傷として残っていることがあると思います。
じゃあ、わたしたちはどうしたらいいの?
わたしたちが苦しみの中で繰り返し感じる「わかってほしかった」という想い。
それは、ほんとうに大切な叫びです。
でも同時に、「親であっても、すべてのニーズを満たすことはできない」という事実を受け入れることができたとき、癒しの扉がそっと開きはじめるのです。
あの痛みの奥にあったのは、「期待」という名前の愛だった
「愛されなかった」と思っていた気持ちの奥には、「本当は愛してほしかった」という切なる願いがあります。
それは、あなただけのものではなく、誰もが心の奥に抱えている、“愛への執着”という名のやさしい記憶。
だからこそ、親への期待を手放すことは、愛をあきらめることではなく、もっと自由な愛を生きる準備でもあるのです。
5. 親との境界線を引くことは、冷たいことじゃない
わたしたちはときどき、「親を遠ざけるなんて、ひどいことなんじゃないか」、「境界線を引いたら、見捨てるみたいで罪悪感がある」そんなふうに思ってしまうことがあります。
でも、境界線とは「拒絶」ではなく、「自分の命を、自分の手に取り戻す」という選択なのです。
自分の宇宙を生きる、ということ
子どもは、はじめは母の宇宙に住んでいます。
そして成長とともに、自分自身の宇宙をつくっていきます。
それは決して「親を否定すること」ではなく、「親とは別のリズムと光を持つ、自分だけの星を生きる」こと。
そのためにはまず、親の価値観や期待という“重力”から、一度ふわりと離れる必要があるのです。
「親の目線」で生きていたわたしから、「内なる声」に従うわたしへ
誰かの目を気にして、「ちゃんとしなきゃ」「期待に応えなきゃ」と生きていた時間。
それも必要なプロセスだったかもしれません。
でも、いまその呪縛をそっとほどいて、「わたしはどうしたい?」という声に、耳を澄ませるときが来たのです。
目に見えない“へその緒”を切る儀式
スピリチュアルな視点では、親との間には“見えないコード”がつながっていると言われています。
それは、肉体を通して育まれた愛や、魂の記憶として結ばれていた絆かもしれません。
けれど、成長のプロセスの中では、そのコードを「ありがとう」と言ってほどく時期が訪れます。
それは親を否定するのではなく、ほんとうに自分を愛するための、魂の自立の儀式なのです。
わたしのハートに、わたし自身で手を当てるとき
他者の評価や、親の期待ではなく、自分のハートがほんとうに求めているものを感じてみる。
誰かに「こうしなさい」と言われる前に、わたし自身に「どうしたい?」と問いかけてみる。
その瞬間から、わたしたちははじめて、本当の意味で愛される存在になるのです。
まず、自分自身に、愛される存在として。
6. 誰も悪くなかった。でももう自由になっていい
「親のせいかもしれない」と思っていた。
でも、そう思ってしまう自分のことも、どこかで責めていた。
わかってもらえなかったことを嘆きながら、「本当は愛されたかった」と思い続けてきた。
その痛みのなかで、ずっとひとりで、がんばってきたのかもしれません。
あなたのその痛みは、ほんとうのものです
誰かに否定されたとしても、過去のことだと言われたとしても、癒されたふりをしてきたとしても、あなたが感じた痛みは本物です。そしてそれは、あなたが弱かったからでも、運が悪かったからでもありません。
それはむしろ、あなたの魂が「ほんとうの自分」に出会うために選んだ、通過儀礼だったのです。
だからもう、自由になっていい
「母の目線」ではなく、「自分のまなざし」で、今日という日を生きていい。
愛されなかった過去を抱えたまま、それでも「わたしはわたしのままで愛される」と信じて、歩いていい。
あなたはもう、誰かの期待を背負わなくていい。
誰かの人生を生きなくていい。
あなた自身の宇宙を生きるために、ここにいるのだから。
親との関係に、愛と痛みが混ざっていてもいい。
まだ癒しきれていなくても、完璧じゃなくてもいい。
誰も悪くなかった。
だからこそ、この瞬間から、あなたはもう自分を許して自分を生きていいのです。