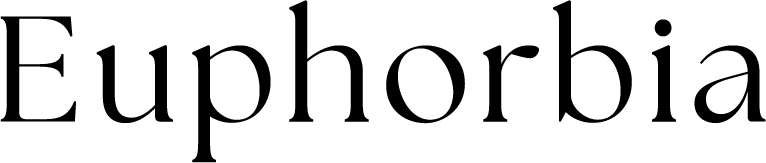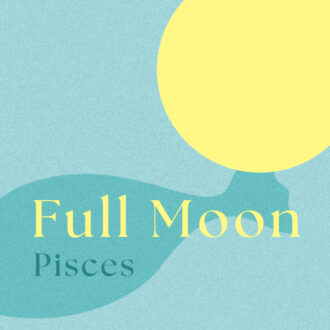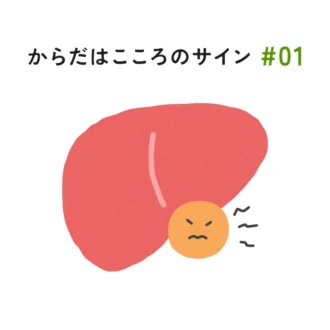麹と味噌と、発酵のある暮らし「わたしを醸す、味噌のちから」(基本の味噌づくり)

Release 2025.07.12 / Update 2025.08.24
ふと、味噌汁の湯気に顔を近づけると、どこか懐かしいような、安心する香りが胸の奥まで届いてくることがあります。
あたたかさの中に、静かな力がある。
味噌には、そんな「わたしを整えてくれる」やさしさが宿っているのです。
INDEX
なぜ今、味噌なのか?
私たちが普段手にする味噌の多くは、すでに「完成された商品」として売られていて、その向こうにある“つくられる過程”や“菌のちから”には、なかなか目が届きません。
実は、味噌というのは、とてもシンプルな素材からできています。
豆(大豆だけじゃなく、小豆やひよこ豆なども)と、麹と、塩。
それだけなのに、びっくりするほど深い味わいが生まれていきます。
それは、時間と菌とわたしたちの手がそっと協力しあって、少しずつ育てていくから。
手前味噌を仕込むということは、「今ここ」のわたしと向き合うこと。
「これから」の自分に、やさしい未来を贈ることでもあるのです。
わたしたちは、日々いそがしく、いろんなことに追われて生きています。
でも、味噌づくりには、そんな暮らしのなかでも“立ち止まる時間”をくれる力があります。
季節のリズムに合わせて豆を炊き、手のひらでこねる。
麹のやわらかい香りに包まれていると、自然と呼吸も深くなります。
それはまるで、自分の内側と手をつなぎなおすような、やさしい作業なのです。
味噌は、わたしたちのいのちを支える「食」であり、時に心に寄り添ってくれます。
麹のこと、味噌の種類、実際の仕込み方など、日々の暮らしにすぐに役立つ実用的なことも、丁寧にお伝えしていきます。
一緒に、味噌と発酵の世界にふれてみましょう。
味噌ってどんな食べもの?
味噌は、日本の食卓にとって、あまりにも当たり前な存在かもしれません。
けれど、その「当たり前」にこそ、深い知恵と、長い時間が刻まれているのです。
味噌は、ゆでた豆に麹と塩を加え、発酵・熟成させてつくる、自然由来の発酵食品。
冷蔵庫も保存料もなかった時代に、人々は知恵と自然の力を借りて、食べものを「生きたまま」保存する方法を生み出しました。
気候が湿潤で四季の変化に富む日本だからこそ、“菌たち”とともに暮らすという発酵文化が、何世代にもわたって育まれてきたのです。
味噌は、ただの調味料ではありません。
たんぱく質、アミノ酸、ビタミン、乳酸菌…
発酵によって生まれるそれらの栄養は、体を芯から整え、心までも穏やかにしてくれます。
特に近年は「腸内環境」が心の健康にも影響するという研究が進み、味噌の持つ“腸にやさしいちから”が、あらためて注目されています。
そして、味噌にはたくさんの種類があります。
・白味噌:甘くてやさしい、関西に多い味わい
・赤味噌:発酵期間が長く、深みのあるコク
・合わせ味噌:白と赤をブレンドした、まろやかな万能タイプ
・豆味噌:東海地方の伝統。大豆と塩だけで仕込む濃厚な味
など。
さらに最近では、大豆のかわりに「小豆」や「ひよこ豆」、「レンズ豆」などを使う人も増えてきました。
小豆は陰性で消化にやさしく、大豆アレルギーのある方にも安心な素材です。
味噌って、実はもっと自由で、もっとやさしい。
わたしたちの体質や好みに合わせて、自分だけの“わたし味噌”を仕込むことができるのです。
知れば知るほど、手をかけたくなる。
味噌は、そんなふうに、日々の暮らしをそっと豊かにしてくれる食べものなのです。
発酵の魔法使い、麹のちから
味噌を味噌たらしめているもの。
それは、豆でもなく、塩でもなく、目には見えない小さな存在、「麹菌(こうじきん)」です。
麹菌は、蒸したお米や麦、大豆などに繁殖し、素材をやさしく分解していく微生物。
でんぷんを甘みに、たんぱく質を旨みに変えていくその力は、まさに“発酵の魔法使い”とも呼べる存在なのです。
この麹菌のちからがあるからこそ、味噌は「塩辛い」だけの調味料ではなく、「奥行きのある、こころに響くおいしさ」へと育っていきます。
麹の種類
麹にはいろんな種類があり、麹の種類によって、味噌の風味はがらりと変わります。
どれを選んでも正解です。大切なのは、自分の体や暮らしに合う“麹と出会う”という感覚なのです。
- 米麹(こめこうじ)
クセがなく、ほんのり甘みのある優しい味わい。
手に入りやすく、はじめての味噌づくりにもおすすめです。 - 麦麹(むぎこうじ)
すっきりとした香りと軽やかな風味。
九州や四国などで親しまれています。夏にも向く軽やかさ。 - 玄米麹(げんまいこうじ)
香ばしく、コクのある仕上がり。
白米よりも栄養価が高く、自然派志向の方に人気です。
「小豆×麹」のやさしい甘み
大豆のかわりに「小豆」を使って仕込む味噌もあります。
小豆は大豆よりも油分が少なく、体を内側から整える“陰性”の豆。
そこに麹を合わせると、ほんのり甘く、まろやかで、まるでデザートのような味噌ができあがるのです。
お味噌汁だけでなく、ドレッシングやスイーツにも応用できるその風味は、ちょっと疲れた心をやさしく撫でてくれるような、そんな味わいです。
麹はからだと心を整えてくれる
発酵によって生まれる酵素や乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力を高めてくれるだけでなく、実は「こころの状態」にも影響を与えてくれることがわかってきています。
腸は“第二の脳”と呼ばれ、感情や思考と密接につながっている場所。
麹の発酵パワーは、体を整えると同時に、どこかざわざわした気持ちを落ち着かせる“内なる静けさ”も連れてきてくれるのです。
こんな時に味噌がパワーをくれる
忙しい日々のなかで、ふと「なんだか疲れたな…」と感じることはありませんか?
そんなとき、体や心の声に気づくのは、けっこうむずかしいことです。
でも味噌は、わたしたちのそんな“ちいさなサイン”に、静かに寄り添ってくれます。
胃腸が疲れているとき
冷たいものや外食が続いたとき、なんとなくお腹が張っていたり、便通が乱れたり…。
そんなときは、あたたかい味噌汁をゆっくりすするだけで、胃腸がほっと落ち着いていくのを感じることがあります。
味噌にふくまれる発酵成分や酵素は、消化を助け、腸内の善玉菌を元気にしてくれます。
しかも、自家製味噌には乳酸菌や酵母がたっぷり。
自然のちからが、やさしく内側から整えてくれます。
からだを温めたいとき
冷えやすい季節、からだの芯まで寒さが入りこんでくるような夜。
そんなときは、具だくさんの味噌汁に生姜やねぎを添えて、身体の奥まで温まるひと椀を。
味噌には、塩分や発酵のちからによって、血流を促す作用もあります。
お風呂あがりに飲むと、汗をかくほどぽかぽかに。
とくに、冬に仕込んだ味噌は、寒い季節との相性もぴったりです。
春先のデトックス期や、月のリズムと合わせて
春は「解毒の季節」ともいわれ、肝臓や腸がいつもよりがんばりやすい時期。
冬にたまった老廃物を手放すためにも、味噌の“整えるちから”が活躍します。
また、女性の体は月のリズムとも深くつながっています。
満月や新月のころ、心や体がゆらぎやすいと感じたら、味噌を使ったやさしい食事で自分を労わってみてください。
たとえば、満月の日は、体を温める根菜の味噌汁でしっかり巡らせる。
新月の日は、小豆味噌のおかゆでリセット&浄化モードに。
発酵食品は、月の引力と調和しやすいともいわれています。
自然とつながる暮らしのなかで、味噌はとても心強いパートナーなのです。
実際に仕込んでみよう!味噌のつくり方
「味噌って、ほんとうに自分で作れるの?」
そう思う方もきっと多いはず。
でも大丈夫。特別な道具がなくても、はじめてでも、ちゃんとできます。
むずかしいことは一つもありません。
手を動かしながら、少しずつ発酵の世界と仲良くなっていけばいいのです。
ここでは、家庭でもできる【基本の味噌づくり】をご紹介します。
使うのは大豆と米麹ですが、同じ手順で小豆や他の豆でもアレンジできます。
材料(できあがり 約2kg分)
- 大豆 … 500g(※小豆やひよこ豆でも可)
- 米麹 … 500g(乾燥でも生でもOK)
- 塩 … 200〜230g(塩分控えめなら200g)
- 保存容器(ホーロー、ガラス、陶器、ジップロックなどでも可)
- ラップ or 和紙・重し用の塩(またはラップとペットボトル)
味噌づくりの手順
1. 豆を水に浸す(前日準備)
豆を洗い、たっぷりの水に12〜18時間ほど浸けます。
2〜3倍にふくらむので、大きめのボウルで◎
※夏場は冷蔵庫で。小豆やひよこ豆は浸水時間が短めでもOK。
2. 豆をやわらかく煮る(当日作業)
鍋でコトコト2〜3時間、やさしく煮ます(圧力鍋なら20〜30分)。
指でつまんで、ふにゃっと潰れるくらいが目安です。
※煮汁はとっておいてあとで調整に使えます。
3. 潰す
温かいうちに、マッシャーや手で豆を潰します。
粒を残してもなめらかでも、お好みで大丈夫。手で潰すと、発酵菌たちとの対話ができるかも^^
4. 麹と塩を混ぜる(塩きり麹)
別のボウルに米麹と塩をよく混ぜ、「塩きり麹」を作ります。
ここに潰した豆を少しずつ加えて、全体をよく混ぜましょう。
※もし固すぎたら、豆の煮汁で調整を。耳たぶくらいのやわらかさが目安です。
5. 味噌玉をつくって詰める
空気が入らないように、野球ボールくらいの「味噌玉」を作って、容器にぎゅうっと詰めていきます。最後に表面をならし、空気が入らないようにラップや和紙で密封。
※カビ防止に、塩をうすくふっても◎
6. 熟成させる
冷暗所で6ヶ月〜1年ほど寝かせます。
夏に仕込めば秋〜冬に、冬に仕込めば夏〜秋に食べ頃に。
途中で白いカビのようなものが出ても、心配ありません。取り除けばOK。
ミニアドバイス
- カビ対策に、月に一度くらい容器の様子をのぞいてみてください(これもたのしい時間です)。
- 小豆や玄米麹で仕込むと、やさしい甘みや香ばしさが増します。
「ちゃんとできるかな」よりも「今の自分の手で作ってみる」ことが、大切なのです。
たとえ味が濃すぎたり、形が不ぞろいでも、味噌は世界でたったひとつのあなたの暮らしの味になります。
発酵は、わたしを育ててくれる
味噌づくりは、「待つこと」が中心にある仕事です。
すぐに完成する料理とちがって、数ヶ月、時には一年という時間を、ただ静かに寝かせる。
目には見えない菌たちが、ゆっくりと味を育ててくれるのを、信じて、待つ。
それはまるで、自分自身を育てる旅と、どこか似ています。
何かを始めてもすぐに結果が出ないと不安になる。
思いどおりにいかない自分に、ついダメ出ししてしまう。
でも、発酵は教えてくれます。
「すぐに見えなくても、ちゃんと育ってるよ」と。
味噌を仕込むということ
手のひらで豆を潰すとき、麹の香りを吸い込むとき、そこには「今ここ」にいる自分との静かな対話が生まれます。
手前味噌は、自分で仕込んだ分だけ、想いがこもります。
うまくできるかどうかではなくて、「手をかける」という愛情が、そのまま味になるのです。
手仕事のなかにある「整える力」
わたしたちがふだん見落としがちな、小さな所作や、時間の流れに耳をすませること。
味噌を仕込むという行いのなかには、そんな“内なる整え”がそっと息づいています。
仕込んだ味噌が、少しずつ色づき、香りを深めていくように、わたしたちの内側にも、言葉にならない変化が起きているのかもしれません。
毎日すこしずつ、味わいが深くなる「わたしの味」
味噌汁をお椀によそって、最初のひと口をすするとき、「こんな味、今までになかった」と思うことがあります。
それはきっと、この手で仕込み、この心で育てた、世界にひとつの“わたしの味”だから。
味噌がわたしたちを育て、そしてわたしたちもまた、味噌を育てている。
発酵のある暮らしとは、そんな静かな往復の旅なのです。
おわりに
味噌を仕込むことは、日々の忙しさの中に、小さな祈りを灯すようなもの。
それは、決して「特別な人」だけのものではありません。
誰の手の中にも、菌とともに生きる力が眠っています。この文章を読み終えたあと、「ちょっとやってみようかな」と思ってもらえたら、とても嬉しいです。
あなたの暮らしにも、やさしく豊かな“発酵のリズム”が流れはじめますように。
そして、あなたという存在が、味わい深く、ますます美しく育っていきますように。